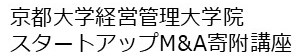2025年7月
Deconstructing Trados: The Option Value under Loss-Cutting Decisions
朝岡大輔・ Journal Article
掲載媒体:Revue Trimestrielle de Droit Financier (RTDF) (Corporate Finance and Capital Markets Law Review) 70, pp. 39-51 (2025)
要約
本稿はスタートアップの資金調達の契約において規定される株主の権利を、オプションの構成要素に分解した上で、この枠組みを、米国におけるベンチャーキャピタル (VC) のイグジットに関する重要判例であるトラドス社 (Trados) の事案の分析に適用するものである。この事案は、同社の優先株式に投資するVCが主導して、いわゆる損切りとして2005年に同社が売却された際、VCは投資を概ね回収できたのに対し、普通株主は何ら回収できなかったことから、普通株主が訴訟を提起したものである。
2013年に判決を出した米国デラウェア州の衡平法裁判所 (Court of Chancery) は、同社が売却された際の普通株式の価値は「ゼロ」であったと判示し、結論としてVC側を支持した。しかし、同判決は、売却の判断を所与として価値を評価しており、オプションの構成要素に含まれる、継続を前提とした時間価値を捨象しているといえる。損切り時に普通株主が被った時間価値の損失額を試算すると、当時あり得たシナリオの中で、損失額は最大値に近い水準であったことが分かる。さらに、契約にはVCによる強制売却権(ドラッグ・アロング・ライト) は存在せず、損失が確定する普通株主は保護されるべきであったという批判が可能である。
損切りの判断は、もはや失うものがない普通株主が、アップサイドを狙って投資期間を引き延ばす、いわゆる資産代替問題のリスクに対して、VCが先手を打つ行動であるともいえ、本判決の後に起こった強制売却権の標準化を含め、有効な契約に基づく決定権にはオプションとしての価値がある。本稿の意義は、投資家間の利益が相反し、タイミングの判断における裁量が重要である損切りという局面において、その判断をコントロールできることのオプション価値を明らかにした点にある。
2025年5月
投資リスクの観点から見た優先株式の評価―考えるヒントとなるオプション評価の応用
朝岡大輔・ Journal Article
掲載媒体:月刊監査役No. 776, pp. 58-72
要約
本稿は、スタートアップの優先株式に関して、その契約の個別性や複雑性を踏まえつつ、オプションの考え方を用いた一定の評価手法を、我が国における典型的な条件に適用して分析するものである。
優先株式は、具体的な契約条件を踏まえて、企業価値の変化に伴う優先株主へのペイオフの変化を分析した上で、オプションの組み合わせに分解することで、ブラック=ショールズモデルに基づく価値の合計として求めることができる。
具体的には、優先株式の契約条件の内、優先株式の投資元本の優先的な回収と参加権は、企業価値全体とコールオプションの組み合わせとして、普通株式への転換権は、転換によって価値が下落するバイナリー・オプションとして捉えることができ、後続するシリーズの優先株式の価値も、先行するシリーズとの優先劣後関係に基づき、行使価格の異なるオプションの組み合わせに分解できる。先行する優先株式の価値は、後続する優先株式の発行自体から本来は影響を受けないが、時間の経過に伴う企業価値の変化の認識や、投資条件の交渉によって価値の移転が起こることで、実際には変化するので、既存投資のリスクの把握の上でも、後続投資の条件の理解は重要である。
優先株式をオプションの組み合わせに分解して見た場合には、企業と投資家の間、普通株式と優先株式の間、そして異なるシリーズの優先株式の間などにおいて、利害が錯綜する。優先株式をオプションとして見ることには、このような利害を、それぞれが保有するポジションの相違として明示的に認識した上で、投資条件の価値やリスクを理解し、必要に応じて判断や交渉に結び付けられる意義がある。
2025年5月
山田和郎・ Journal Article
掲載媒体:第5期JSDAキャピタルマーケットフォーラム
要約
スタートアップ企業への投資の増加傾向にある現状において,その出口の一つとしてのIPO市場のあり方についての議論が盛り上がりつつある。とはいえ,そのような議論の中には,過剰な期待にもとづくものも存在するように見受けられる。そのうえで,本稿ではIPOにおける機関投資家の役割について整理する。過去の先行研究を確認する限りでは,個人投資家は機関投資家と比較して非合理的であるとされている。一方で,IPO株式の過半が個人投資家に配分されるという実態がある。本稿の実証パートでは,IPO後の株主の推移を確認することで,機関投資家が参加するタイミングについて検証を行った。一般的に言われるように「時価総額100億円」までは,時価総額が高まるほど機関投資家の投資確率が高まることが確認された。さらに,IPO後一定期間(ここでは1年間)の間に機関投資家からの投資がなかった場合,その後に投資を行う頻度が低下することが分かった。続いて,機関投資家の参入前後での株価の変化について分析を行った。機関投資家が投資を行ったタイミングで一時的な株価の上昇が確認された。最後に,IPO価格決定メカニズムについて,現状の手法(ブックビルディング)での問題点を克服する手法としてのハイブリッド方式を提案する。